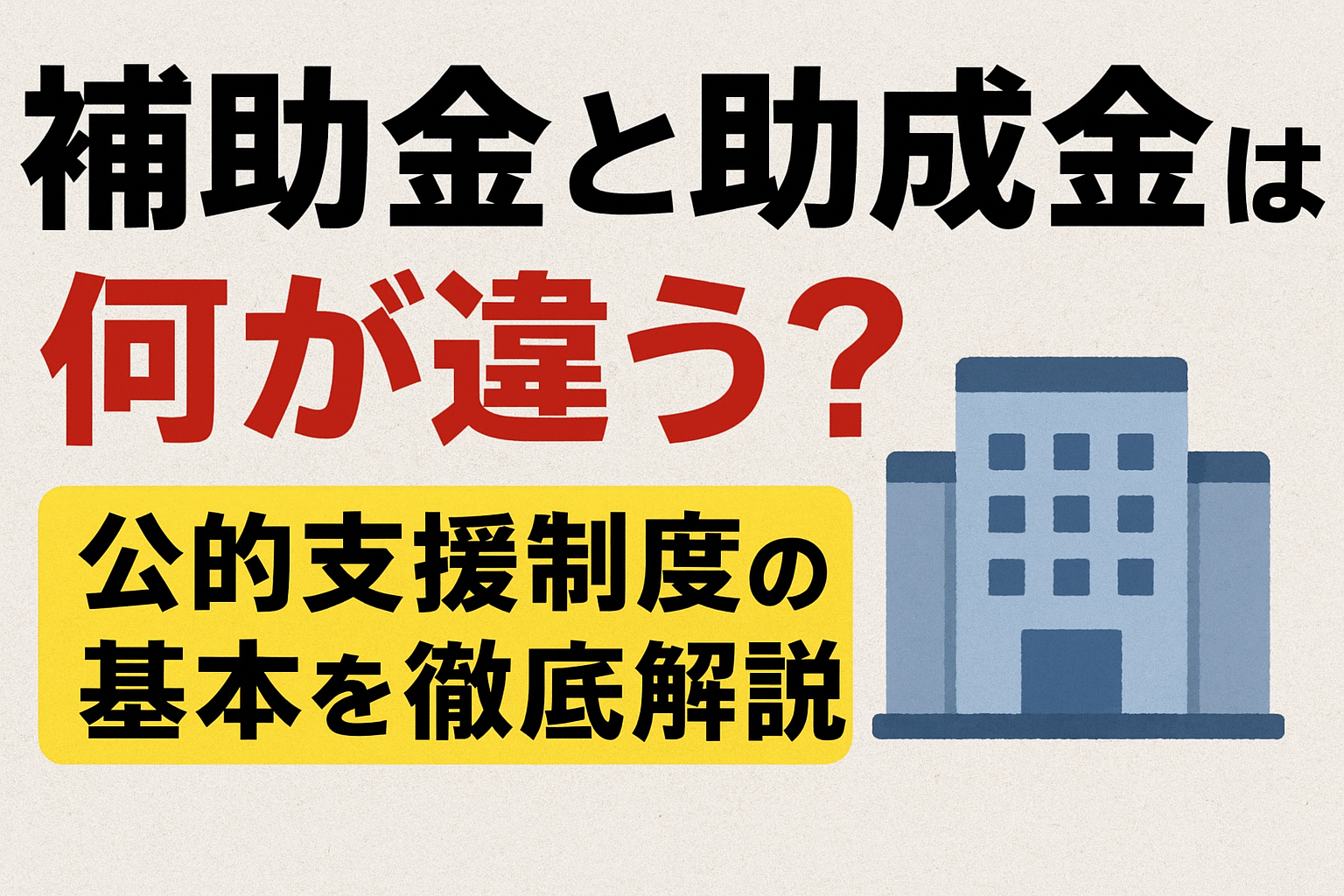なぜ「補助金」と「助成金」の名称は混ざるのか?
事業拡大や新しい挑戦を考える際、国や自治体の「補助金」や「助成金」は非常に強力な味方になります。しかし、「結局、何がどう違うの?」「どちらの名称で検索すればいい?」と疑問に思う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、経済産業省の制度が「補助金」、厚生労働省の制度が「助成金」と呼ばれることが多いですが、慣習的なものですので、事業主の皆様は名称(補助金・助成金)そのものに神経質になる必要はありません。
大切なのは、誰が何を目的としてその制度を出しているかを知ることです。
この記事では、公的支援制度を発行元(管轄官庁)ごとに整理し、それぞれの特徴と活用方法を分かりやすく解説します。
1. 経済産業省(経産省)系:経済活性化と「未来の投資」を支援する「補助金」
✅ 目的:新しい挑戦と事業拡大を後押しする
経産省(主に中小企業庁が担当)の制度は、中小企業の新規事業、研究開発、生産性の高い設備投資など、日本経済の成長加速化に貢献する取り組みを重点的に支援します。
✅ 特徴:競争があり、採択・不採択が決まる「選抜型」
審査が厳格: 提出された事業計画が政策目的に合致し、将来的に大きな収益を生むかを審査されます。競争原理が働き、採択・不採択が明確に分かれます。
公募期間が限定的: 申請できる期間が短く、計画的な準備が必要です。
対象経費: 建物(施設整備)、機械装置、ソフトウェア開発・導入など、事業の「資本」となる大規模な投資が中心です。
💡 代表的な補助金(2025年11月現在)
【組織体制】 経産省系の補助金は、経産省⇒中小企業庁⇒中小企業基盤整備機構を経て、多くはパソナなどの民間企業が事務局として実施しています(持続化補助金は商工会・商工会議所が窓口)。
2. 厚生労働省(厚労省)系:雇用環境整備を促す「助成金」
✅ 目的:企業の「人」に関する課題解決を支援する
厚労省の制度は、雇用安定、人材育成、労働環境の改善など、「労務関連の制度を整えること」を目的としています。これが、経産省の「事業投資」との決定的な違いです。
✅ 特徴:要件を満たせば原則支給される「条件達成型」
要件を満たせば原則支給: 制度に定められた「要件」(例:就業規則の変更、研修の実施)をクリアすれば、原則として助成金が支給されます。ただし、過去の不正受給対策として、現在は厳正な審査のもと、不支給になるケースもあります。
労務管理が必須: 労働基準法や雇用保険法などに則り、適切に労務管理ができていることが大前提となります。
申請代行: 労務関連の手続きを含むため、申請代行は社会保険労務士(社労士)の独占業務です。社労士に依頼する場合は申請用紙に印鑑が必要ですが、ご自身で申請することも可能です。
💡 代表的な助成金
・キャリアアップ助成金: 非正規雇用労働者のキャリアアップを促進。
・業務改善助成金: 生産性向上と事業場内最低賃金の引き上げを支援。
・人材開発支援助成金: 職業訓練などを実施する事業主を支援。
3. 自治体(都道府県・市区町村):地域に特化した「補助・助成制度」
✅ 目的:地域課題の解決と独自政策による地域経済の活性化
各自治体(都道府県、市区町村)が、その地域特有の課題(例:後継者不足、商店街活性化)や独自の政策目標に合わせて設定する支援制度です。
✅ 特徴:名称は「補助金」「助成金」どちらも使われる
名称は混在: 自治体が独自に設ける制度は、目的や審査形式に関わらず、「補助金」と「助成金」のどちらの名称も使われることが多いため、名称にはこだわらず内容を確認しましょう。
自治体差が大きい: 予算が潤沢な自治体(例:東京都)は支援制度が充実していますが、財政が逼迫している自治体では制度が限定的になる傾向があります。
きめ細かな支援: 市区町村の補助制度では、SNS広告やHP作成など、小規模で単発の取り組みが対象になることも多く、小回りが利きやすいのが特徴です。
【東京都の例】 特に東京都は、しごと財団や中小企業振興公社が窓口となり、都内の中小企業向けに非常に充実した支援メニューを提供しています。
まとめ
補助金も助成金も、貴社の事業を力強く後押ししてくれる公的支援です。制度の名称に惑わされることなく、あなたの「未来の事業投資」の目的に合った制度を見つけ、積極的に活用しましょう。